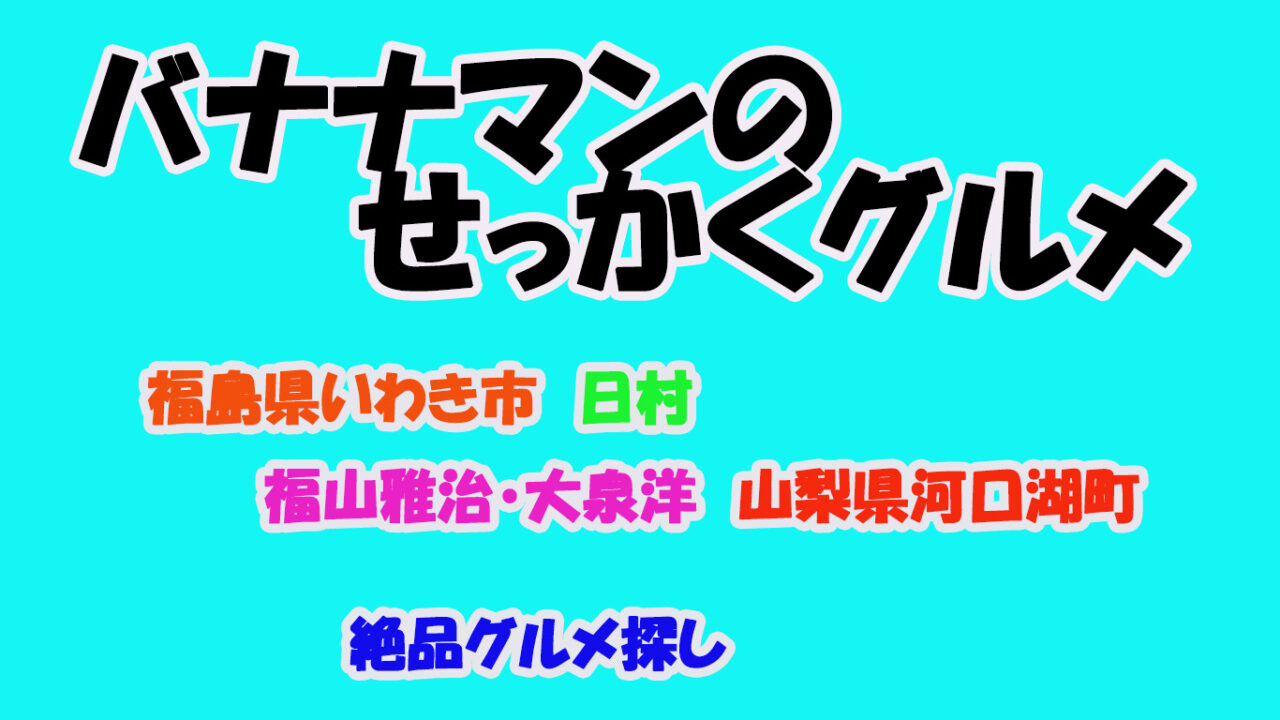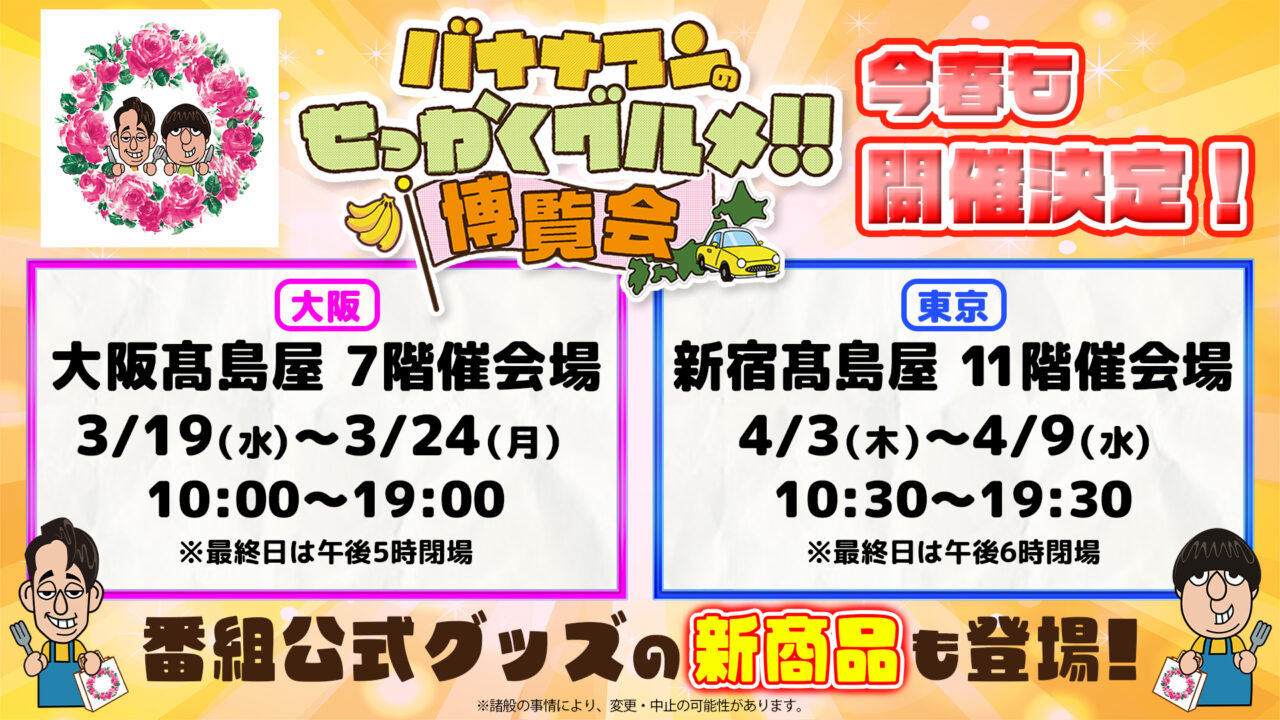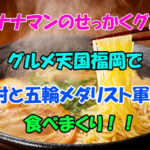Table of Contents
はじめに: 期待を背負う2つの「後継機」の現状
キヤノンのミラーレスシステムにおいて、EOS R7とEOS R6 Mark IIはそれぞれAPS-Cとフルサイズの「中核」を担うモデルとして、高い評価を得てきた。EOS R7は、その高速性、望遠効果、そしてトリミング耐性により、スポーツや野生動物の撮影を得意とするユーザーから絶大な支持を受けている。一方、EOS R6 Mark IIは、万能なフルサイズセンサーと優れた動画性能により、幅広いクリエイターに愛用されている。その次世代機であるEOS R7 Mark IIとEOS R6 Mark IIIには、市場の期待がかつてなく高まっている。しかし、現時点で入手できる情報は公式なものではなく、複数の情報源から発信される様々な噂に過ぎない。

この画像は生成AIで生成したイメージ画像です。
本稿は、これらの信頼性の低い噂と、複数の情報源から確度が高いと見られる情報を峻別し、両機種の噂される全貌を多角的に分析する。単なるスペックの羅列に留まらず、それがキヤノンの製品戦略や、ユーザーの撮影体験にどのような影響をもたらすか、深い洞察を提供する。現行モデルの成功を踏まえ、キヤノンが次にどのような進化を志向しているのか、そしてそれが市場にどのような影響を与えるのかを詳細に探っていく。
パート1: 予想されるAPS-Cの旗艦モデル – EOS R7 Mark II

この画像は生成AIで生成したイメージ画像です。
1-1. スペックから読み解く「高級路線」への転換
EOS R7 Mark IIの最も注目すべき点は、そのスペックが示唆する「高級路線」への転換である。現行のEOS R7は、約6年前に発売されたEOS 90DやEOS M6 Mark IIと同じ約3250万画素のセンサーを搭載していると指摘されており 、センサー技術の刷新は多くのユーザーが待ち望んでいた要素だ。噂では、後継機は「約40MP」 または「33MP」 への画素数向上に加え、積層型APS-C CMOSセンサーの搭載が示唆されている 。これは、読み出し速度の大幅な改善を意味し、APS-Cセンサーにおけるローリングシャッター効果を最小限に抑える上で不可欠な要素となる。このセンサーの進化は、キヤノンがAPS-Cを単なるエントリーレベルのシステムではなく、プロおよびハイアマチュア向けの「ハイエンド」市場に引き上げようとする明確な意図を反映している 。
動画機能もまた、飛躍的な進化が噂されている。具体的には、8K動画撮影 や、プロ向けのカラースペースであるC-Log3に対応した4K120p撮影 といった、これまでのAPS-C機では考えられなかったプロ仕様の機能が加わるとされている。これにより、R7 Mark IIは静止画だけでなく、動画制作においても強力なツールとなるだろう。
さらに、プロセッサにはDIGIC XとDIGICアクセラレーターの組み合わせが採用され 、手ブレ補正は8.5段分もの強力なボディ内手ブレ補正(IBIS) が噂されている。これらの機能は、EOS R5 Mark IIに匹敵する処理能力と安定性を提供し、過酷な撮影環境でも安定したパフォーマンスを発揮する。
1-2. デザインとユーザーエクスペリエンスの進化
R7 Mark IIのボディは、現行R7よりも大きくなるものの、キヤノンの他のラインナップと同様に軽量さは維持されるとされている 。エルゴノミクスは、現行R7よりもEOS R5 Mark IIに近いものになり、操作性の統一性が図られる 。これにより、APS-Cとフルサイズのシステムを併用するプロにとって、よりシームレスな撮影体験が提供される。また、冷却グリップなどEOS R5 Mark II用のアクセサリーとの互換性も示唆されており 、プロ向けのシステムとしての完成度がさらに高まる。
一方、電子ビューファインダー(EVF)に関しては、236万ドットのものが搭載されると噂されており 、一部のユーザーからは失望の声が上がっている 。しかし、フォーラムの議論では、バッテリー寿命が延びるという利点や、スポーツ・野鳥撮影といった特定の用途では、被写体の追跡に集中するため高解像度が必須ではないという意見も存在する 。これは、EVFの解像度とバッテリー寿命の間のトレードオフに対する、ユーザーの異なる優先順位を示している。
1-3. 決定的な議論の核心 – 機械式シャッターの行方
最も注目されている噂の一つは、Rシリーズとして初めて機械式シャッターを廃止し、電子シャッターのみとなる可能性だ 。この大胆な決断は、コスト削減や可動部品の排除による故障リスクの低減というメリットをもたらす 。ニコンは既にZ8やZ9といったプロ機で同様の選択をしており、ミラーレスカメラの進化における必然的な流れと見なされている。
しかし、この変更は、R7 Mark IIの主要なターゲット市場である高速な被写体を扱う野鳥・野生動物写真家からの懸念を引き起こしている。電子シャッターで高速な動き(特に鳥の羽など)を撮影した際に発生するローリングシャッター歪みは、彼らのワークフローにおいて深刻な問題となりうる 。この機能の採用は、新世代センサーの読み出し速度に対するキヤノンの自信の表れであると同時に、技術的な挑戦とユーザーニーズの板挟みにあることを示唆している。もし、噂される積層型センサーが既存のR7(ソニーのハイエンド機よりも読み出し速度が速いと評価されている) をはるかに上回る高速読み出しを実現できれば、ローリングシャッターの問題はほぼ解消され、ユーザーは40fpsという驚異的な電子シャッターでの連続撮影 やプリ連続撮影 を安心して活用できる。この場合、R7 Mark IIは、その分野における「ゲームチェンジャー」となる。しかし、それが不十分であれば、ターゲットユーザーの信頼を失いかねないリスクを抱えている。
パート2: 磨き上げられたフルサイズハイブリッド – EOS R6 Mark III
2-1. 噂される核となる性能向上
EOS R6 Mark IIIは、前世代機で高い評価を得たバランスの取れた性能をさらに磨き上げる方向性が噂されている。まず、センサーの画素数に関しては、24MPから30-32MPまで幅があるものの 、EOS R3由来の積層型センサーを搭載する可能性が指摘されている 。この積層型センサーは、高速な読み出しと高感度性能の両立を可能にし、特に低照度環境での撮影に強みを発揮する 。
動画性能の強化も顕著だ。6K RAW 60fps や4K120fps に対応し、さらにC-Log2およびC-Log3が追加されるとの情報もある 。現行のR6 Mark IIがC-Log1のみであることを考慮すると、これはプロの動画クリエイターにとって待望のアップグレードとなる 。また、EOS R5 Mark IIレベルの高度なオートフォーカスシステム と、8段にまで向上するIBIS性能 が噂されており、静止画・動画を問わず、安定した撮影をサポートする。
2-2. 筐体と操作性の変化
R6 Mark IIIは、ソニー製ミラーレスカメラを模倣した、チルトとバリアングルを組み合わせた新デザインの液晶が噂されており 、さらにキヤノン初の有機EL(OLED)モニターが搭載される可能性も示唆されている 。これは、キヤノンが他社で成功したユーザーエクスペリエンス(UX)の要素を積極的に取り入れ、自社の製品ラインナップに統合しようとしていることを示している。新しい液晶デザインとOLEDモニターの搭載は、主に動画撮影やvloggingといった用途を意識した進化だ。これにより、R6 Mark IIIは写真と動画のどちらにおいても最高のパフォーマンスを発揮する「真のハイブリッド機」として、市場に再定義されるだろう。これは、特にマルチメディアクリエイター層からの支持を狙った、キヤノンの明確な戦略と見られる 。
価格は、R6 Mark IIの発売価格2,499ドルよりも高くなるものの、3,000ドル以下に抑えられるとの噂がある 。これは、R5 Mark IIのようなハイエンドモデルとの明確な差別化を図りつつ、性能向上に見合った価格設定として、市場で「バリューチャンピオン」としての地位を確立する可能性がある 。
パート3: R7 Mark II vs R6 Mark III – ユーザーの選択を分ける決定的な違い
キヤノンがEOS R7 Mark IIとEOS R6 Mark IIIをほぼ同時期に発表する可能性は、ユーザーにとって「どちらを選ぶべきか」という重要な問いを突きつけることになる 。この選択は、単なるスペックの比較ではなく、自身のクリエイティブな目的とワークフローにどちらがより適しているかという、より深い検討を要する。以下の表は、両機種の主要な噂スペックを比較し、その違いを明確に示している。
3-1. 予想スペック詳細比較表
| 項目 | キヤノン EOS R7 Mark II (噂) | キヤノン EOS R6 Mark III (噂) |
| センサー | 約40MPまたは33MP APS-C 積層型CMOS | 24MP-32MP フルサイズ 積層型CMOS |
| 静止画連写速度 | 40fps (電子シャッター) | 不明(高速連写が期待される) |
| 動画性能 | 8K動画 、4K120p 、C-Log3 | 6K RAW 60fps 、4K120p 、C-Log2/3 |
| シャッター | 機械式シャッター廃止の可能性 | 機械式/電子シャッター |
| 手ブレ補正 | 8.5段分 | 8段分 |
| EVF | 236万ドット | 240万-360万ドット |
| カードスロット | CFexpress Type B + UHS-II SD | CFexpress + UHS-II SD |
| 予想価格 | 1,700-2,000ドル | 2,799-3,199ドル |
| ターゲット市場 | 高速な被写体、望遠重視 | 低照度、オールラウンドなハイブリッドクリエイター |
この比較表は、両機種が互いに食い合うことなく、異なるユーザープロファイルに最適化された全く別の製品であることを明確に示している。R7 Mark IIの「高画素・高倍率・高速」という方向性は、明確な専門用途(スポーツ、野鳥、航空機)を志向しており 、高解像度センサーによるトリミング耐性と高速な連写性能は、この分野のプロ・ハイアマチュアにとって最大の武器となる。一方、R6 Mark IIIの「バランス・高感度・高機能動画」という方向性は、低照度下の撮影(結婚式、ライブなど)や、ポートレート、そしてプロフェッショナルな動画制作を行う、より汎用性の高いハイブリッド機としての地位を確立しようとしている 。フルサイズセンサーがもたらす豊かな階調とノイズ耐性、そして高度な動画機能は、オールラウンドなハイブリッドシューターにとって理想的だ。
3-2. 「フルサイズかAPS-Cか」という永遠の問いへの答え
これまでのAPS-C対フルサイズの議論は、画質と望遠効果のトレードオフが中心だった。しかし、R7 Mark IIとR6 Mark IIIの世代では、その議論は「特定の専門用途に特化した性能」か「万能なハイブリッド性能」か、というより戦略的で深い次元に移行する。
キヤノンが両機種をほぼ同時に発表することで、ユーザーに対し、「どちらかを選ぶ」というより「自分のクリエイティブなニーズに最も合致するツールを選ぶ」という明確な選択肢を提示している。EOS R7 Mark IIは、APS-Cの強みである望遠効果と高速性を極限まで高めた、小型でありながらプロレベルの性能を持つ「スペシャリスト」としての地位を確立する。一方、EOS R6 Mark IIIは、あらゆるジャンルの撮影を高いレベルでこなすことができる「ジェネラリスト」としての役割を担う。このポートフォリオ戦略は、ユーザーの多様化するニーズに細かく対応するための、キヤノンの製品ラインナップの完成形を示している。
結論: 噂のその先へ
本レポートで分析した情報はあくまで「噂」であり、公式発表で覆される可能性も大いにある。しかし、これらの噂が示す方向性は、キヤノンのミラーレスシステムが次のフェーズへと移行していることを強く示唆している。
EOS R7 Mark IIは単なるAPS-C機ではなく、トップティアの技術を凝縮した「プロ仕様の小型・高速機」として、R6 Mark IIIは「手の届く価格帯でプロ機並みの機能を持つ」ハイブリッド機として、それぞれが異なる市場を再定義する。両機が揃うことで、キヤノンは初心者からプロまで、あらゆるユーザーを網羅する、より強固で論理的なラインナップを確立することになるだろう。
最終的な判断は、公式発表と実機レビューを待つ必要がある。しかし、現時点で言えることは、キヤノンが提示しようとしている未来は、写真家やビデオグラファーにとって、これまで以上に魅力的でエキサイティングなものであるということだ。